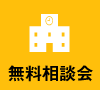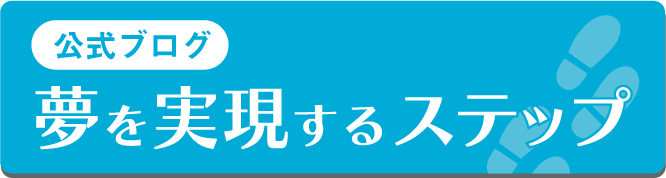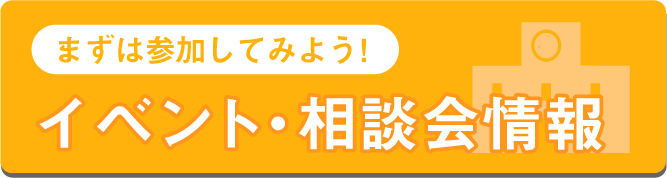日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#3、4、5~わたしはどれを買えばいい?~
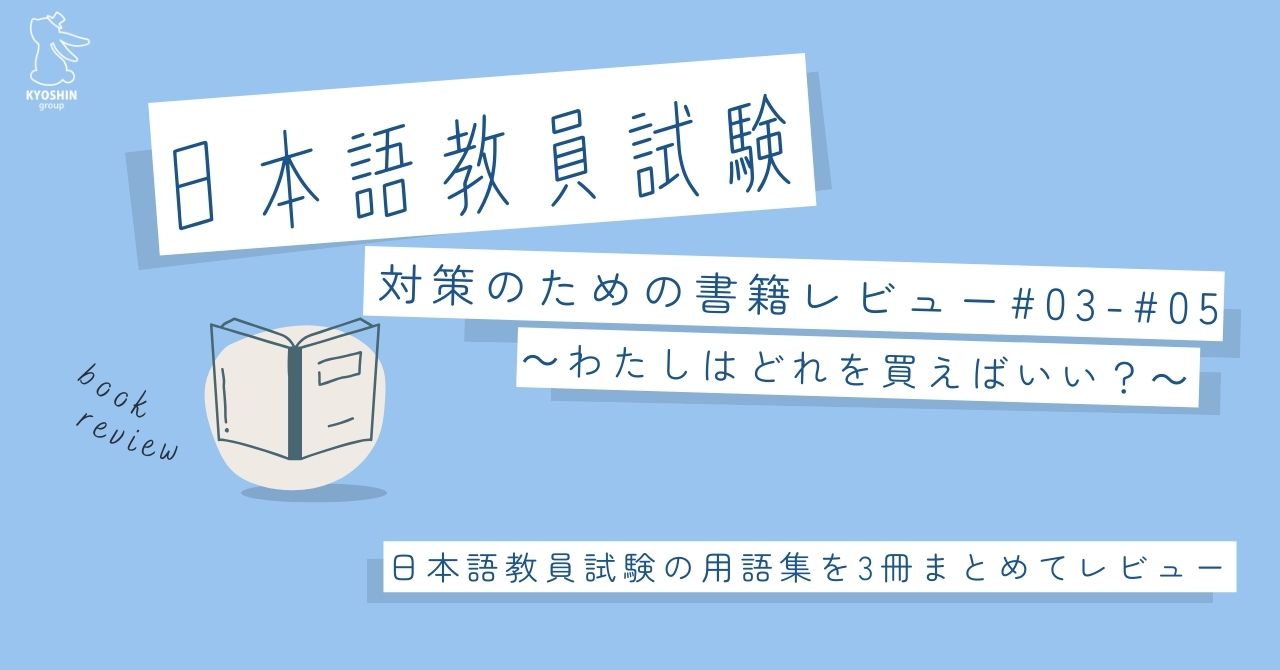
シリーズ「日本語教員試験 対策のための書籍レビュー」#3~#5
このシリーズは、
- ・試験傾向が見えないので、どの本が役に立つのか判断できない
- ・近くに大型書店がなく、中身を見ずにネットで買うしかない
- ・書名が似たようなものばかりで、違いが分からない
- ・今のわたしに合う本は?
そんな声に応えるべく、シリーズ「日本語教員試験 対策のための書籍レビュー~わたしはどれを買えばいい?~」と題して、本音のレビューをお届けしています。忖度なし、ステマなし、実際に「対策を行っている立場」ならではの視点から、本当に役立つ一冊を見極めるお手伝いができれば幸いです!
#1「日本語教員試験「応用試験 読解」解ける500問(コスモピア)」
#2「講義形式で学ぶ 日本語教員試験 攻略テキスト(アスク出版)」
に続き、第3弾は日本語教員試験に対応した用語集3冊について、一気にご紹介します。
結論から言えば、いずれも優れた用語集なので、複数を買う必要はなく、いずれか1冊あれば十分です。このコラムはそれぞれの特徴や強みを整理し、自分の学習スタイルや目的に合った1冊を選ぶ参考にしていただければと思います。
目次
- ➊教材紹介#3『日本語教員試験対策用語集』
- ◆多くの方に勧めやすい定番の用語集
- 安定の一冊
- 新教員試験に向けたアップデートは限定的
- 電子書籍で読めるのはうれしい。クイズ機能はおまけ程度に
- 教材紹介#3 まとめ
1教材紹介#3『日本語教員試験対策用語集』
まず1冊目は、『日本語教員試験対策用語集』(アルク)をレビューします。
◆多くの方に勧めやすい定番の用語集
長年、多くの受験生に支持されてきた『日本語教育能力検定試験に合格するための用語集』が、『日本語教員試験対策用語集』としてリニューアルされました。表紙も小豆色からロイヤルブルーに一新され、装いも新たに登場しています。
安定の一冊
日本語教育の世界で共通理解とされてきた重要な用語が丁寧に収録されており、解説も簡潔で非常に読みやすい構成です。私たちが運営する講座でも長らく使用してきた、信頼できる一冊です。
新教員試験に向けたアップデートは限定的
日本語教員試験対応にするため、「日本語教育の参照枠」や「登録日本語教員」など、最重要項目が追加されています。ただここまでの試験からわかっている出題傾向から、もう少し踏み込んで用語を追加していってほしいところです。例えば、「バックワードデザイン」「自己評価/ピア評価」「ICT」「LMS」「自律学習」「JFT-Basic」などの用語が未収録です。また新試験で重要性が増す「著作権」や授業実践に関連する項目についても、解説の更新は限定的という印象です。
電子書籍で読めるのはうれしい。クイズ機能はおまけ程度に
電子書籍派にとって、本を買えば電子版も閲覧できる点は、独自の電子書籍リーダーアプリというところさえ気にならなければ朗報!付属のクイズもありますが、アプリのインターフェースや問題構成の観点から、「毎日の学習に」というよりおまけ程度に考えておいた方がよいかもしれません。
教材紹介#3 まとめ
『日本語教員試験対策用語集』(アルク)
総じて非常にバランスが良く、これからの対策に向けて安心して使える一冊です。
| ✔日本語教育の基本用語を丁寧かつ簡潔に解説。 ✔新試験対応のキーワードが今後さらに充実してほしい。 ✔電子書籍対応で手軽。クイズは補助的に活用を。 |
2教材紹介#4「日本語教員試験 合格キーワード1400(晶文社)」
次に2冊目、『日本語教員試験 合格キーワード1400』(晶文社)をレビューします。
◆試験に出るキーワードを取りこぼしたくない方に最適
本書は、もともと「日本語教育能力検定試験」の対策書として出版されていたものを、増補・改訂して再刊した用語集です。
図表を多用した視覚的な構成
「図表でスッキリわかる」という副題の通り、視覚的な補助が挿入されているのが特徴です。中には「これは表にしなくてもいいのでは…」と感じる箇所もありますが、直感的に理解したい方にとっては親しみやすい一冊です。
徹底したキーワードの網羅
制作者が旧検定試験含め、過去の出題傾向を徹底的に分析している印象を受けます。「とにかく過去問に出た用語は載せる」という気概を勝手に感じました。例えば、私が教員試験の試行試験や第1回試験で「このことばはよく知らないな…」と感じてメモしていた以下の用語があります。
──「防衛機制」「エンパシー」「共同発話」「接触仮説」──
これらは日本語教育の一般的な共通理解からは離れているかな、と感じるのですが、それらのすべてが本書に収録されていました。ある程度の“捨て問題”を想定する方にとっては情報過多になるかもしれませんが、それでも「何でも載っている」という安心感が光る一冊です。制作者が旧検定試験含め、過去の出題傾向を徹底的に分析している印象を受けます。「とにかく過去問に出た用語は載せる」という気概を勝手に感じました。
解説のわかりやすさと統一感
用語解説は、初学者にとって必要最低限かつわかりやすい記述がなされています。また、一人の著者によって書かれているため、文体や情報量にムラが少ない印象です。一方で、「社会構成主義」や「複言語主義」といったやや専門的な用語については、その分野の専門家による記述というよりも、不正確な表現を極力避けながら、初学者に向けてやや単純化して書いている印象もあります。
巻末資料が充実
国際音声記号や口腔断面図、日本語文法と学校文法の活用表、「日本語教育の参照枠」の要点まとめなど、実用性の高い資料が豊富です。
教材紹介#4 まとめ
『日本語教員試験 合格キーワード1400』(晶文社)
想定されるキーワードを隅々まで網羅した一冊です。「試験に出た言葉が用語集に載っていないとモヤモヤする」という方にとっては、ベストな選択肢となるでしょう。
| ✔視覚的に理解しやすい図表が豊富。巻末資料も充実。 ✔過去の出題から、やや中心から外れた用語までカバー。 ✔専門的な記述というより、初学者にも伝わりやすいシンプルな用語解説。 |
3教材紹介#5『日本語教員試験基本用語集(アスク出版)』
最後に3冊目は、『日本語教員試験基本用語集』(アスク出版)をレビューします。
◆絶妙な見出し語の選定と専門家の知見が光る一冊
本書は、新たに始まった「日本語教員試験」に向けてゼロから執筆された数少ない用語集のひとつです。既存の検定試験用参考書を改訂した他2冊と比べると、より新制度に対応した内容が期待できます。
見出し語のバランスと構成が試験に最適化
基本的な用語をしっかり押さえつつ、著作権やICTといった新試験向けの項目もページを割いて扱われています。強いて言えば、『日本語教育の参照枠』 に関する解説がやや薄いのと、「行動中心主義」「ICT」といった重要項目が見出し語として立っていないのがやや気になりますが、作成過程で様々な判断があったのかと。全体としては絶妙なバランスであると感じます。
専門家による解説
本書は各セクションごとに執筆者が分かれています。
東京外大学系列の執筆陣だけあって、言語系はしっかり書かれていますし、専門家の間でも理解に差のある「社会・制度」関連についても「Web情報から定義だけを何となくまとめた」ような書き方にはなっていません。また「状況的学習論」のような端的な説明が難しい、用語集泣かせの項目も、専門的な理解を基に(何とか)まとめています。セクション「評価法とテスト」については、あの評価法の大家・伊東祐郎先生の執筆という贅沢っぷりです。
かといって専門的過ぎて難しいということはなく、初学者でもわかるように解説されています(セクションごとに多少ムラがある気もしますが)。ただ、図表やイラストなどの視覚的補助がもう少しあると、初学者にとってさらにとっつきやすくなりそうです。
もう少し見た目が洗練されていれば
これは読み手の好みではあるのですが、レイアウトやフォント、余白や挿絵などの問題なのか、ペラペラページをめくったときにやや素朴な印象を受けました。見やすくはあるのですが、用語集3冊をパッと見比べられたときに、少し損をするかもくらいの具合です。また巻末に参考資料がついていないのも、用語集だけで比較した際、表面的な差異として感じられるかもしれません。
攻略テキストとの併用は?
本書は同社の『講義形式で学ぶ日本語教員試験 攻略テキスト』とシリーズになっています。基礎試験の合格を目指す方には、「攻略テキスト」はテーマごとの体系的な理解、一方「用語集」はキーワード単位での理解と、用途に応じて使い分けて活用するといいでしょう。両者の記述内容について、重なる部分はありますが、テキストの記述がそのまま抜粋されて用語集になっているわけではないので、その点ご安心ください。
一方、応用試験の合格を目指す方が、横に置く参考図書として本書を検討しているのであれば、用語集のみでも事足りそうです。
教材紹介#5 まとめ
『日本語教員試験基本用語集』(アスク出版)
本書の一番の魅力は、日本語教員試験用にゼロから作成されたこともあり、新試験に最適化された見出し語と構成で、そのバランス感は随一です。また各専門家による解説の信頼度も高いです。
| ✔新試験に最適化された見出し語と構成。 ✔基礎試験対策をしたい方は、同じシリーズの「攻略テキスト」とセットで使うと〇。 ✔視覚的補助は少なめだが、解説の精度と信頼性は高い。 |
カテゴリー: 日本語教員試験 日本語教師の国家資格 | 2025.09.13
最近の記事
- 【保存版】日本語教員試験応用試験2(読解)得点予測チェックリスト
- 【保存版】日本語教員試験応用試験1(聴解)得点予測チェックリスト
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#3、4、5~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#2~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#1~わたしはどれを買えばいい?~
カテゴリー
- コロナ禍の日本語教育~養成講座からオンライン授業の今を見る~ (6)
- ミャンマーで教える (ヤンゴン校) (5)
- 事務局からKLAニュース (66)
- 教務ブログ (51)
- 日本語教師について知る! (8)
- 日本語教師の国家資格 (10)
- 養成講座提供のイベント・インターンシップ等 (21)