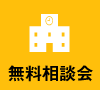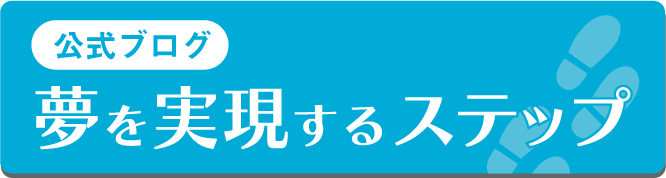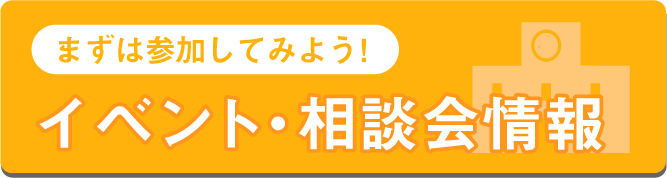日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#2~わたしはどれを買えばいい?~
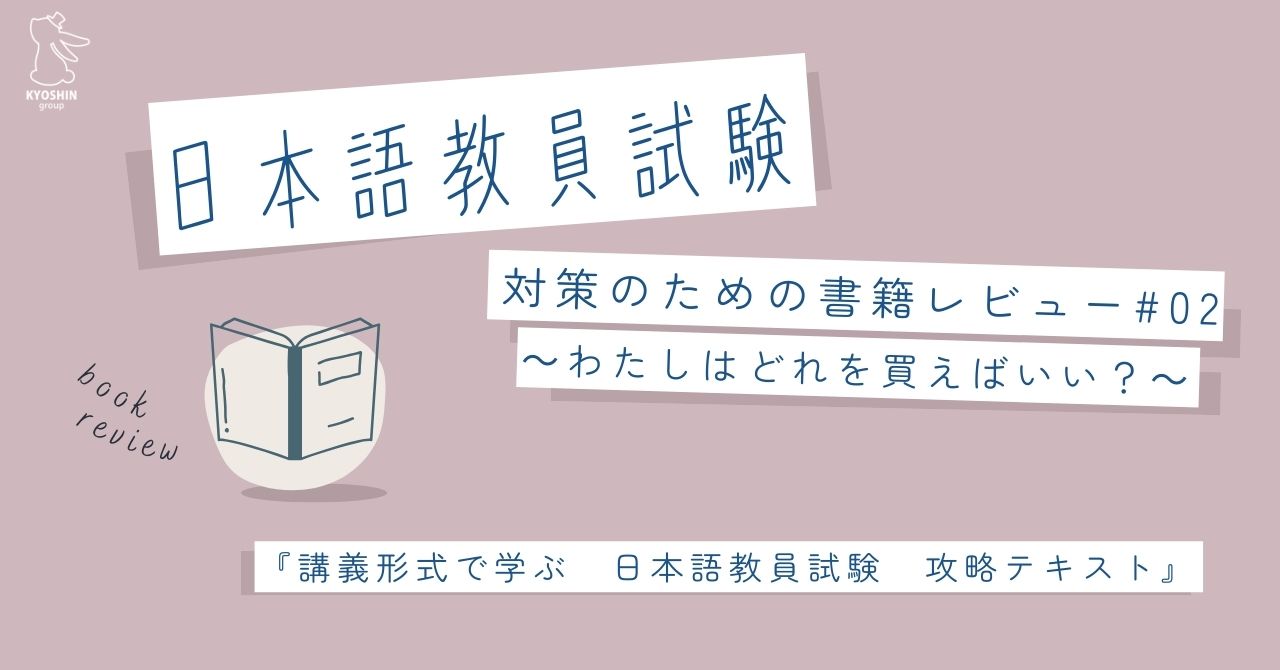
シリーズ「日本語教員試験 対策のための書籍レビュー」#2
前回からスタートした当シリーズ。たくさんの方に読んでいただいており、ありがとうございます!
このシリーズは、
- ・試験傾向が見えないので、どの本が役に立つのか判断できない
- ・近くに大型書店がなく、中身を見ずにネットで買うしかない
- ・書名が似たようなものばかりで、違いが分からない
- ・今のわたしに合う本は?
そんな声に応えるべく、シリーズ「日本語教員試験 対策のための書籍レビュー~わたしはどれを買えばいい?~」と題して、本音のレビューをお届けしています。忖度なし、ステマなし、実際に「対策を行っている立場」ならではの視点から、本当に役立つ一冊を見極めるお手伝いができれば幸いです!
本日は2冊目のレビューをお送りします。
目次
1教材紹介#2『講義形式で学ぶ 日本語教員試験 攻略テキスト』
第2回目は、日本語教育に関心のある方を対象に数多くの著作を出されている、東京外国語大学・荒川洋平先生による『講義形式で学ぶ 日本語教員試験 攻略テキスト』(アスク出版)をレビューします。
書籍の概要(出版社の内容紹介より抜粋)
国家資格となった「日本語教員試験」に完全対応の参考書です。 全40回の講義形式のテキストで、出題範囲の知識を網羅することができます。基礎試験を受験される方におすすめ! より深めたい方むけに、ブックガイドやコラムも掲載しており、日本語教師のキャリアを通じて役立つレファレンスとなります。
特徴1)試験範囲を網羅的に学習できる
本書は、いわゆる「教科書」です。これ一冊で、ゼロから体系的かつ網羅的に日本語教員試験の出題範囲を学ぶことができます。
新試験で重視される「著作権」「ICT」「日本語教育の参照枠」、また教育実践に関わる項目についてもしっかりページが割かれており、解説内容も新試験への対応を意識したものとなっています。また、各単元の重要度が星で示されているのも親切ですね。
2025年7月時点で、日本語教員試験に特化した「教科書」は他にほとんどなく、このタイプの書籍を必要とする方にとっては、ほぼ唯一の選択肢です。
特徴2)全40回の定期的な学習に向く構成
文部科学省が示している日本語教育の学習項目の区分として、5分野、必須の50項目があります。
……が、個人的には区分けの厳密さ不足や、後から項目追加していったような恣意性からその区分に不満を持っています。
一方、本書はその区分にこだわらず、単元や項目を再構成して全40回で立てられています。その構成は文科省の区分よりも、よっぽどしっくりくるもの、かつ教員試験構成を踏まえたものに見事に組み直されています。
全40回、おおよそ同じ分量で組まれており、各回のタイトルもテーマが端的にわかるようになっているため、毎日〇分、毎週〇回などの、定期的・習慣的な学習をするのにぴったりです。
特徴3)豊富な練習問題
本書は章ごとの理解確認のための練習問題のほか、オンラインドリルという練習問題が全300問もあり、通勤中などのすきま時間にスマートフォンで取り組むこともできます。「教科書」でありながら、かなり太っ腹ですね。各設問には対応するテキストのページが示されており、復習や理解の確認にも便利です(ちなみにテキスト自体は持ち運びするには大きく重量があります)。
2「よし、買おう!」その前に…
購入の前に知っておいてほしい点をまとめました。
本書は「基礎的な知識」の理解のための本
本書は、試験対策の「最初の一歩」として優れた内容であり、特にゼロから「基礎試験」に向けて学習を始める方には最適です。
一方で、すでにある程度の知識や経験を有し、「応用試験1・2」の対策に特化して学習を進めたい方にとっては、学習効率の面でロスが大きくなる可能性があります。「基礎試験」と「応用試験」では頻出する範囲や問題形式には異なりがあるためです。そのような方が本書を活用する場合、「わからない言葉に出会ったときに確認する参考書」という用途と考えたほうがいいでしょう。ただその役割は用語集で事足りると感じるかもしれません。
同様に、オンラインドリルを含め、本書の練習問題は基礎知識の定着を目的としており、応用試験への直接的な対策にはなっていません。また、「応用試験1(聴解)」に直結するような内容も見られず、あくまでその前提知識を身につけるための一冊と捉えるとよいでしょう。
初学者がゼロからこれ一冊で基礎試験の合格を目指せるか?
前述したように、本書はゼロから体系的かつ網羅的に試験範囲をカバーする、唯一の「新日本語教員試験の教科書」で、「基礎試験」の対策として有用です。
ただ本書のみを使ってゼロから基礎試験の合格ラインを目指そうとしている方はご注意ください。
というのも、第1回の基礎試験の合格率はわずか8.7%(経過措置対象者除く)で、こと基礎試験に関して言えば、「すべてを自学のみで進める」という方法自体、誰にでも推奨できるとは言えないからです。
もちろん同等の難易度の資格取得を自学で達成した経験がある方や、絶対がんばる!という意志がある方であれば、本書を使っての学習を応援します。
本書の「書き方」との相性は?
このようないわゆる「教科書」の類書としては、ヒュー◯ンの旧検定試験向け完全攻略ガイド等がありますが、それらと比較した際、本書には著者・荒川先生による語りかけるような文体と話の膨らみがあります。その特徴を感覚的に言えば、「短期間で論点だけ端的にを一気に詰め込む」というよりも、読み物として楽しんで読みたい。もっと言えば、毎日単元ごとにオーディオブックなんかで聞きたい内容だと個人的には感じました。
また、ナビゲーターの「ペンタ君」が読者目線で質問を挟んでくれる工夫もありますが、基本的にはテキストを読み進める形式なので、「読むこと」に苦手意識がある方には向いていないかもしれません。表が時折挿入されていますが、図解のようなビジュアル要素がさほど多い本ではありません。
そのあたりは最終的には相性なので、出版社のサイトで公開されているサンプルなどで、まずは一度中身をご覧になるのがおすすめです。
オンラインドリルの用途を確認
オンラインドリルの問題数は多く、基礎知識を問う良問が揃っています。ただし、内容は5分野のざっくりとした分割でそれぞれ約50問、一定の順番で解いていく形式(=50問前後を一気にとく)となっており、「毎日単元ごとに10問ずつ解きたい」というような使い方は想定されてません。
そのため、全体の総仕上げや分野ごとの自己理解度のチェック、または本書に取り掛かる際の苦手ポイントのチェック等、用途が限定されています。
3まとめ
『講義形式で学ぶ 日本語教員試験 攻略テキスト』(アスク出版)
本書は、ゼロから日本語教員試験の基礎試験学習を始める方、あるいは参考図書として用語集以上の体系的な内容を求める方におすすめできる、良質なテキストです。
| ✔ゼロからまずは「基礎試験」の合格を目指したい方 ✔応用試験まで時間に余裕があり、じっくりと「学び直し」をしたい方 ✔参考図書として「用語集」ではなく、体系的な「教科書」を横において学習したい方 |
カテゴリー: 日本語教員試験 日本語教師の国家資格 | 2025.08.22
最近の記事
- 【保存版】日本語教員試験応用試験2(読解)得点予測チェックリスト
- 【保存版】日本語教員試験応用試験1(聴解)得点予測チェックリスト
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#3、4、5~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#2~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#1~わたしはどれを買えばいい?~
カテゴリー
- コロナ禍の日本語教育~養成講座からオンライン授業の今を見る~ (6)
- ミャンマーで教える (ヤンゴン校) (5)
- 事務局からKLAニュース (66)
- 教務ブログ (51)
- 日本語教師について知る! (8)
- 日本語教師の国家資格 (10)
- 養成講座提供のイベント・インターンシップ等 (21)