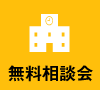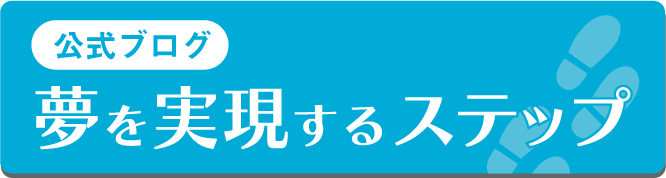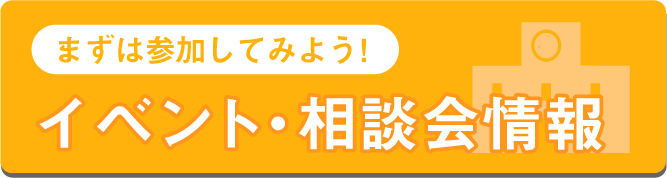日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#1~わたしはどれを買えばいい?~
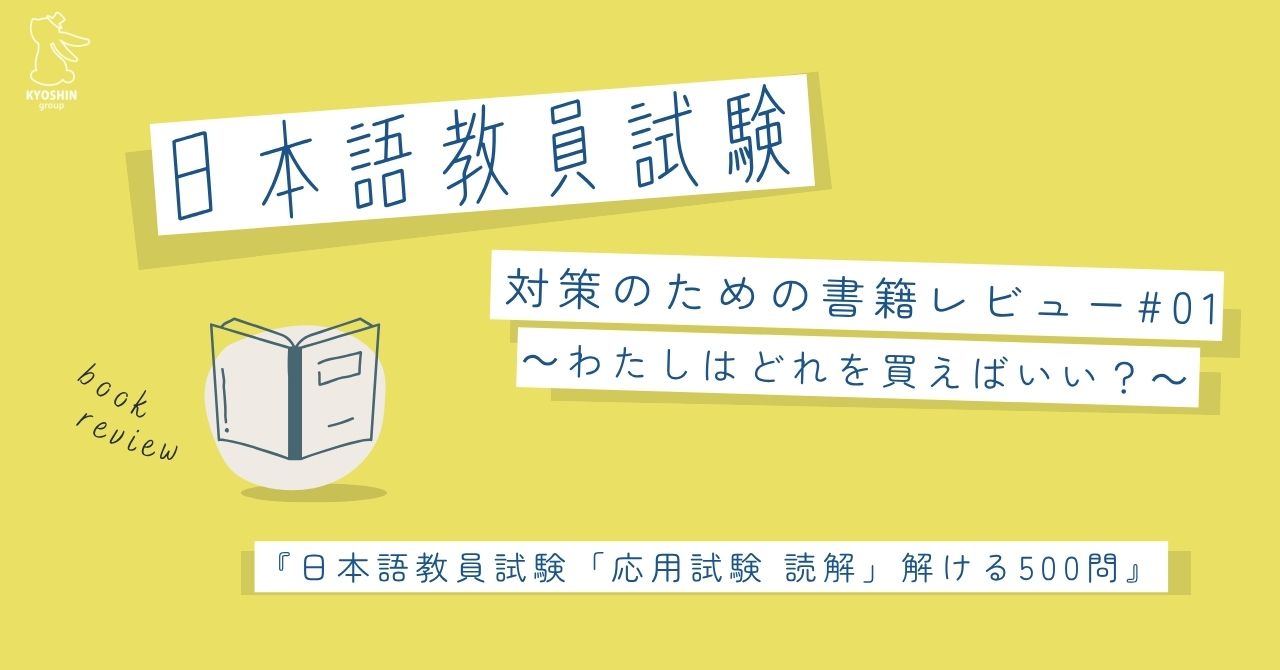
日本語教員試験「対策」の現状
2024年度から「日本語教員試験」が始まり、日本語教育にこれから関わりたい人、また既にかかわっている人の多くの通り道となりました。しかしまだ始まって間もないこともあり、試験の情報は多くありません。そのような状況で、頼りになるのが、いわゆる対策本。数は少ないながらも、新たに「日本語教員試験」という名前のついた書籍も少しずつ登場してきました。とはいえ、これから受験を考える方にとっては、「どの本を選べばいいのかわからない!」というのが正直なところではないでしょうか。
- ・試験傾向が見えないので、どの本が役に立つのか判断できない
- ・近くに大型書店がなく、中身を見ずにネットで買うしかない
- ・書名が似たようなものばかりで、違いが分からない
- ・今のわたしに合う本は?
そんな声に応えるべく、シリーズ「日本語教員試験 対策のための書籍レビュー~わたしはどれを買えばいい?~」と題して、本音のレビューをお届けします。忖度なし、ステマなし、実際に「対策を行っている立場」ならではの視点から、本当に役立つ一冊を見極めるお手伝いができれば幸いです!
目次
1教材紹介#1『日本語教員試験「応用試験 読解」解ける500問』
第一回目は、日本語教育界の大御所坂本正先生の監修本『日本語教員試験「応用試験 読解」解ける500問』(コスモピア)をレビューします。
書籍の概要(出版社の内容紹介より抜粋)
合格するには、試験範囲の全体像を把握すること、体系的・計画的な学習をすること、そして実践応用力を養成することが不可欠です。全500問という圧倒的な問題量をこなして、出題傾向に慣れましょう。(出版社の内容紹介より抜粋)
特徴1)問題量が多い。解説も端的でありながら丁寧。
ハンディな厚さの割に、ぎっしりと問題が詰まっており、かつレイアウトも見やすいです。また、すべての設問に解説がついており、その説明も端的かつ行き届いています。
特徴2)学び直しの方にも親切
4部に分かれており、セクションが進むにつれ易→難と段階付けられています。「過去に日本語教師養成講座等でしっかり勉強したけど、忘れているだろうな」という方でも、Part1のキーワードに関する二択問題を通して、「あー、こんなこと、前に勉強したな」と思い出しながら復習することができます。ある程度、既に理解が進んでいる人でも、最初から取り組むことで「取りこぼし」を見つけることができます。
特徴3)日本語教員試験の出題傾向を踏まえている
「対策本」という意味では、この要素が最も重要かもしれません。これまでの出題傾向から、授業・試験・教材・学習者対応など教育の実践面に関わる項目や、日本語教育参照枠・著作権といったテーマが応用試験2では目立ちます。それに対し本書は、前書きに「徹底的に分析して」とあるように、実際の試験で出題頻度が高そうなトピックにしっかり焦点があてられて設問が作成されている印象です。
特徴4)日本語教員試験の出題形式と同じ
日本語教員試験の応用試験2は、大問12問 × 各5問の小問という構成です。また大問では、教師間の話し合いや指導場面など、具体的な実践場面が設定されているのも特徴です。本書はこれらの形式を反映しており、出題形式に慣れるという意味でも有用です。
2「よし、買おう!」その前に…
購入の前に知っておいてほしい点をまとめました。
「応用試験2」に特化した「問題集」であること
本書は応用試験2(読解)の対策に特化しており、応用試験1(聴解)の対策は一切ありません。応用試験の合否には、むしろ聴解の方がカギとなるケースも多いため、学習時間が極端に限られている方はまず聴解対策を優先してもよいでしょう。
また本書は、ゼロから体系的に学びたいという方を対象とした内容でもありません。分野ごとに整理された「教科書」ではなく、出題が予測される分野の問題にどんどん触れていくための「問題集」です。現時点で学習経験がないなど、ゼロに近い方が始めるには、本書の前にもう1ステップが必要だと考えます。
「完全予想問題集」ではない
本書は、実際の試験で出題が予想されるテーマや問題形式を的確に捉えてはいますが、応用試験の性質上、出題内容を完全に予測することはそもそも困難です。ある出題頻度の高いテーマで予想問題を作るとしても、事例の設定や観点の立て方には無数のバリエーションがあるため、「そのすべてを網羅すること」「ピンポイントで的中させること」自体が現実的ではありません。
また、新試験制度では基礎的な問題は「基礎試験」に移されている傾向があります。しかし「何が基礎で、何が応用か」の線引きはそもそも曖昧なものです。本書にも「これは基礎では?」と思う、例えば、用語の定義を問うような設問もいくつか含まれているように感じました(それらも実際の解答に役立つという判断があると思いますが)。
本書に限らず、問題集に取り組む際の心構えとしては、「このような場面ではこう考えるのが適切、といった判断の方向性を、抽象化して体にしみ込ませていくためのもの」として取り組むと考えるとよいでしょう。そうすることで、実際の試験でも落ち着いて選択肢を絞る力が自然と身についていくはずです。その意味では本書は非常に有用な一冊です。
3まとめ
『日本語教員試験「応用試験 読解」解ける500問』(コスモピア)
本書は応用試験2(読解)対策として、とにかく問題量をこなしたい全ての方にまずおすすめしたい一冊です!
旧・日本語教育能力検定試験を焼き直しただけのような教材も見られる中で、本書は新しい日本語教員試験を、きちんと分析した本当の「対策本」です。また、京進ランゲージアカデミーの応用試験対策コースとの親和性も高く、コースを受講した後の「追い勉」として用いるのも非常に効果的です。
| ✔実際の試験と同じ形式でひたすら問題を解きたい方 ✔過去の学習を「思い出すこと」から始めたい方 ✔既に理解が進んでいる方 ✔京進ランゲージアカデミー応用試験対策コースの受講が終わって、その理解を基に「追い勉」をしたい方 |
カテゴリー: 日本語教員試験 日本語教師の国家資格 | 2025.07.27
最近の記事
- 【保存版】日本語教員試験応用試験2(読解)得点予測チェックリスト
- 【保存版】日本語教員試験応用試験1(聴解)得点予測チェックリスト
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#3、4、5~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#2~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#1~わたしはどれを買えばいい?~
カテゴリー
- コロナ禍の日本語教育~養成講座からオンライン授業の今を見る~ (6)
- ミャンマーで教える (ヤンゴン校) (5)
- 事務局からKLAニュース (66)
- 教務ブログ (51)
- 日本語教師について知る! (8)
- 日本語教師の国家資格 (10)
- 養成講座提供のイベント・インターンシップ等 (21)