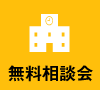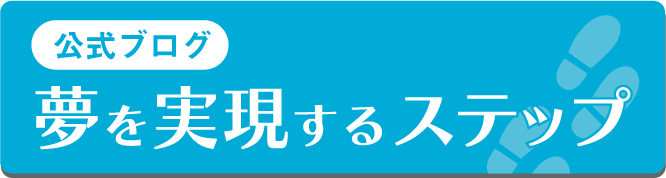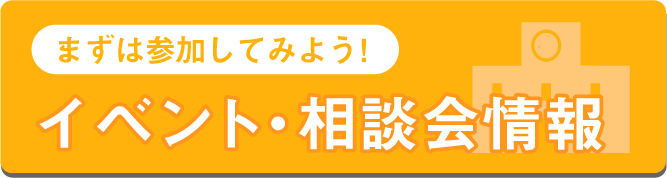【日本語教員試験第1回】と【試行試験】を現役講師が比較解説-2025
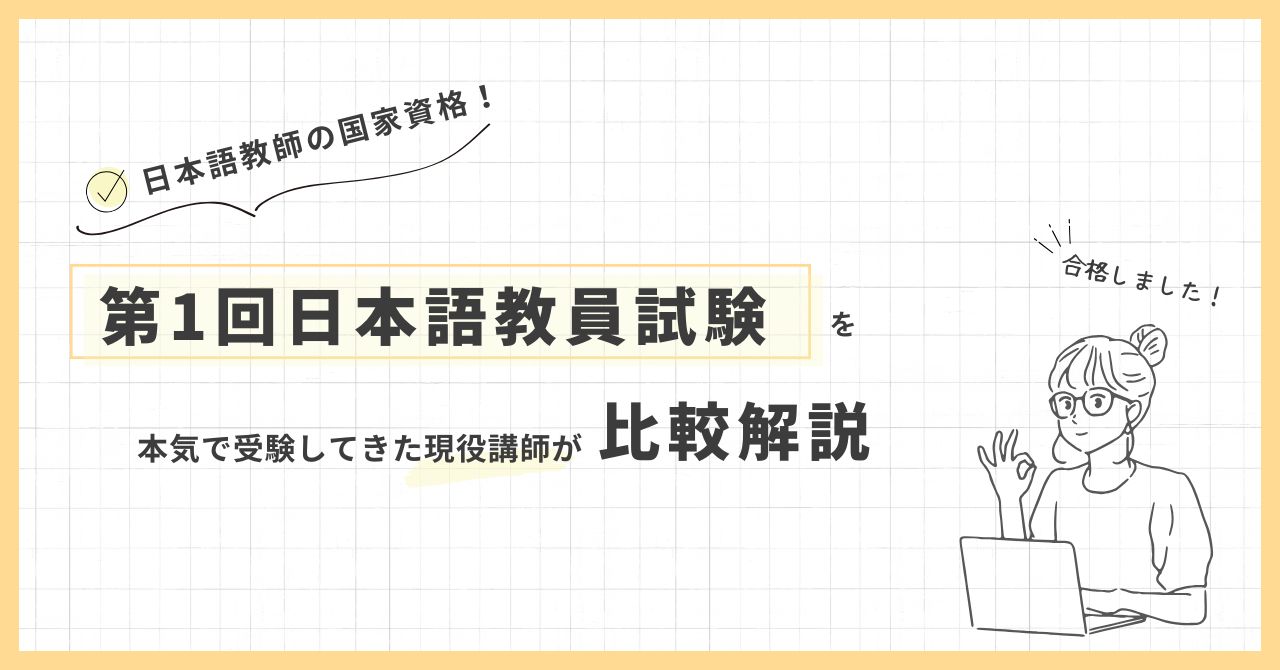
このコラムでは、2024年11月17日に実施された【第1回 日本語教員試験】を本気で受験してきた現役の日本語教師養成講座講師が試験内容をレポートします!今回、私は「登録日本語教員」の資格取得のため、基礎試験と応用試験を受験する必要がある経過措置Fルートで受験し、無事合格しました。
ここでは、2024年実施「第1回日本語教員試験」と2023年実施「日本語教員試験 試行試験(以下、試行試験)」を比較しながら解説していきます。 この情報が現役の日本語教師の皆さまや、登録日本語教員の資格取得を目指す方々の日本語教員試験対策に役立てば嬉しいです。
※本文の内容は2024年11月17日に実施された「第1回日本語教員試験」と2023年12月10日に実施された「試行試験」に基づいて執筆しています。今後の「日本語教員試験」については出題内容や形式が変更されることがあります。
※以下の資料で試験内容や問題例、試験結果が公表されています。合わせてご覧ください。
『令和6年度日本語教員試験実施結果について (PDF:463KB) 』
『令和7年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題 (PDF:1.2MB) 』
| ✔日本語教師の国家資格「登録日本語教員」を取得したい人 ✔「日本語教員試験」を受験する予定の人 ✔現行の制度で日本語教師として働いている人 ✔日本語教師養成講座(文化庁届出受理)を受講中、または修了した人 |
目次
1【第1回日本語教員試験】基礎試験
このセクションでは第1回日本語教員試験の基礎試験を解説します。
基礎試験の難易度は?
試行試験より難しいと感じました。試行試験では基本的な用語の意味を理解しているかが問われるものが比較的多かった印象ですが、第1回日本語教員試験では用語を理解した上で、もう少し深堀りした知識が問われていた印象です。「用語を覚えれば、大丈夫」から一気に、「日本語教育能力検定試験の試験Ⅰが解けないと厳しい」というくらいまで難易度が上がっています。
基礎試験の出題内容は?
必須の教育内容で定められた5区分から満遍なく出題されています。試行試験と同様、コミュニケーションや日本語教育の参照枠に関する設問が多かった印象を受けました。個人的にはもう少し日本語文法に関する設問があってもいいように感じました。また、著作権に関する設問やICTを活用した遠隔授業など、近年の日本語教育の動向に関する設問も盛り込まれていました。
基礎試験の所感「最大の難関は”合格基準”」
基礎試験は試行試験より難しくなったものの、日本語教育の専門家でないと太刀打ちできない試験というわけではありません。おそらく、日本語教師養成講座修了レベルでも6~7割くらいの得点は可能だと思います。しかし、日本語教員試験実施要領には、「必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること」と記載されています。この「8割の得点」という基準が高いため、基礎試験の合格率を低下させる一因になっているように思います。ちなみに、私の試験結果は基礎試験87点(100点満点中)でした。日本語教師養成講座の講師でも簡単にクリアできるわけではありませんでした。
2【第1回日本語教員試験】応用試験Ⅰ 聴解
このセクションでは第1回日本語教員試験の応用試験Ⅰ「聴解」を解説します。
応用試験Ⅰ(聴解)の難易度は?
試行試験と同程度、または少し難しいと感じました。試行試験の時点で聴解は難しい印象だったため、本試験では難易度が下がることを期待していましたが、そうはなりませんでした。試行試験と同様、音声は1度しか流れず、試験会場の環境にもよる可能性がありますが、音声がやや聞き取りにくいと感じました。
応用試験Ⅰ(聴解)の出題内容は?
問題の構成は試行試験と大きく変わらず、音声も1度しか流れませんでした。出題内容は音声、文法、聴解教材、さらに、学習者対応や誤用訂正も出題されました。また、知識として問う設問だけではなく、学習者から受ける相談や誤用対応に関する設問もあり、日本語教育の現場での実例が基になっている内容でした。また、聴解教材も四択問題だけではなく、多様な形式が取り上げられており、普段聴解教材に触れる機会が少ない日本語教師未経験者にとっては難易度が高いように感じました。
応用試験Ⅰの所感「現場事例は必須!」
試行試験と同様、日本語教育の現場で遭遇する学習者からの質問、誤用、学習者対応からの出題がありました。知識を問うだけでなく、学習者への質問や誤用に対して迅速に対応できる能力が測られているように感じました。現役日本語教師であれば、「この質問、現場でよくあるな」と共感できるでしょう。言い換えれば、現場での瞬発力を問う問題は現役日本語教師が有利だと感じました。日本語教師経験がない方でも、最近では日本語教育のケーススタディを扱った書籍が出版されています。そうした書籍を活用し、現場事例に触れることで準備を進めるのも良い方法と言えます。
3【第1回日本語教員試験】応用試験Ⅱ 読解
このセクションでは第1回日本語教員試験の応用試験Ⅱ「読解」を解説します。
応用試験Ⅱ(読解)の難易度は?
試行試験とほぼ同じ程度に感じました。出題傾向は異なるものの、日本語教育能力検定試験の試験Ⅲ(記述を除く)に近い難易度です。
応用試験Ⅱ(読解)の出題内容は?
試行試験と同様に、実際の教育現場に関連する設問が中心でした。授業プランや授業の運営に関する設問はもちろん、ここでもICTや日本語教育の参照枠など、新しい教育内容が取り上げられていました。教案や実際の学習者対応に関する設問が多く、現役日本語教師ならどこかで見たことある、あるいは、学生とこのようなやり取りをしたなど、一度は日本語教育の現場で遭遇したことがある内容になっています。
応用試験Ⅱの所感「現役教師も専門用語はマスト」
応用試験Ⅱ(読解)は現役日本語教師なら直感的に解答できる設問がある一方で、専門用語がわからないと解けない設問もあります。実際、私の友人(現役日本語教師)は「用語がわからなくて、何問かさっぱり意味がわからなかった…」とこぼしていました。応用試験であっても、基本的な用語を押さえておくことは必須です。
4【第1回日本語教員試験】まとめ
ここからは第1回日本語教員試験全体を通しての感想を共有します。
長丁場の試験、ペース配分をイメージしよう
基礎試験と応用試験の全てを受験すると、朝10時から夕方4時30分まで試験があり(途中1時間の休憩あり)、とにかく長かったです。基礎試験からずっと頭をフル回転させなければならず、長丁場の試験に慣れていない方には集中力が続かないという印象を受けました。私は応用試験Ⅰの聴解で全集中力を使い果たしてしまい、応用試験Ⅱの長文読解は集中して読むことができず、かなり駆け足で読んでしまったと後で思いました。集中力を満遍なく振り分けるのは難しいですが、試験が4時30分まで続くというのは頭の片隅に置いておくことをおすすめします。
解答時間はちょうどいいのでは
解答時間について、日本語教育能力検定試験ほど「時間が足りない!急いで解かないと!」という印象はありませんでした。基礎試験、応用試験Ⅱ(読解)ともに私は30分ほど時間があまり、見直す時間も十分に取ることができました。一方、私の友人(現役日本語教師)は見直す時間がなかったと言っていました。急いで解く必要はないものの、のんびりも解いていられない、試験時間としては妥当だと感じました。
推しは『日本語教育の参照枠』
日本語教員試験全体を通して「日本語教育の参照枠」が至るところに出題されました。理論の知識だけでなく、「日本語教育の参照枠」の考え方に基づいた授業実践に関する問題も出題されていました。ただ「日本語教育の参照枠」という言葉を覚えるだけでは足りず、「しっかり理解して、実際の授業でも活かしなさい」という並々ならぬメッセージを感じました。ボリュームがある内容ですが、日本語教員試験の受験を検討されている方は必ず「日本語教育の参照枠」には目を通して、いや、読み込むことをおすすめします。
※本文の内容は2024年11月17日に実施された「第1回日本語教員試験」に基づいて執筆しています。実際の「日本語教員試験」については出題内容や形式が変更されることがあります。
カテゴリー: 日本語教員試験 日本語教師の国家資格 | 2025.05.23
最近の記事
- 【保存版】日本語教員試験応用試験2(読解)得点予測チェックリスト
- 【保存版】日本語教員試験応用試験1(聴解)得点予測チェックリスト
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#3、4、5~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#2~わたしはどれを買えばいい?~
- 日本語教員試験 対策のための書籍レビュー#1~わたしはどれを買えばいい?~
カテゴリー
- コロナ禍の日本語教育~養成講座からオンライン授業の今を見る~ (6)
- ミャンマーで教える (ヤンゴン校) (5)
- 事務局からKLAニュース (66)
- 教務ブログ (51)
- 日本語教師について知る! (8)
- 日本語教師の国家資格 (10)
- 養成講座提供のイベント・インターンシップ等 (21)